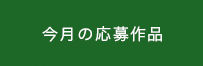俳句庵
季題 7月「夏草」
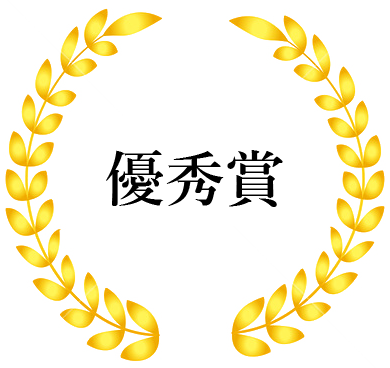
- 夏草に噎せつつ父母の墓を訪ふ
- 熊本県 貝田 ひでを 様
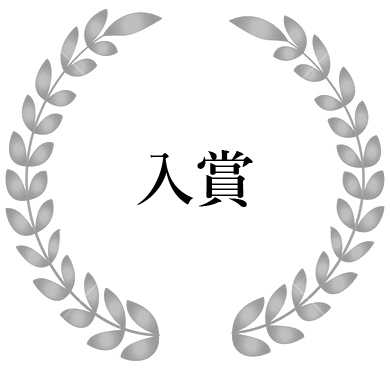
- 牧牛の一日にれかむ夏の草
- 長野県 木原 登 様
- 夏草や時間の止まる生家跡
- 東京都 岩崎 美範 様
- 分けいりて夏草匂ふ草千里
- 福岡県 西山 勝男 様
選者詠
- 灯台へ夏草の丈揃ひけり
- 安立 公彦
安立公先生コメント
夏草の句で最もよく知られているのは、〈夏草や兵共(つわものども)がゆめの跡 芭蕉〉でしょう。周知の通り『奥の細道』平泉高館での作(1689年)。326年も前の句です。歳月という時空に褪せることなく、今でも第一級の俳句作品として輝いています。
優秀賞の貝田さんの句。昔の墓地は、人里離れた土地にありました。かねて気にしながら暫くご無沙汰をしていた両親の墓に、漸く参ることになった作者。「夏草に噎せつつ」に、四辺の情景も活写され、更には、父母への思いも感じられて来ます。
木原さんの句。牧場に放し飼いにされている牛。「にれかむ」は「齝む」と書き、牛が反芻することです。「一日にれかむ」に、牧場の牛たちの景がのびやかに表現されています。尚「夏の草」は「夏草」の傍題です。
岩崎さんの句。「生家跡」は作者の生れた家の跡地。おそらく都市部を離れた地方でしょう。作者にとっては久しぶりに訪れた古里です。しかし生家跡の変貌に立ち尽す作者。「時間の止まる」に、その思いがよく出ています。夏草が効果的です。
西山さんの句。「草千里」は阿蘇山の火口跡の草原です。「分けいりて」に、夏草の生い茂る草原の雄大さが的確に出ています。
今月も佳句が多いでした。〈夏草の匂ふや戦後七十年 鈴木綾子〉。〈夏草や礎石のみなる城の跡 井手浩堂〉。〈臥して見るいのち眩しき夏の草 佐藤博一〉。それぞれテーマは異なりますが、内容は立派です。
俳句は季節と共に在る日本固有の伝統詩です。四季の存在する日本ならではの詩形です。その四季を表す言葉の中から「季節の言葉」即ち季語が誕生し、俳句歳時記が出版されました。季語に託した皆さんの俳句をお待ちしております。
◎ 優秀賞、入賞に選ばれた方には、山本海苔店より粗品を進呈いたします。